V・E・フランクル『それでも人生にイエスと言う』

V・E・フランクル『それでも人生にイエスと言う』
山田邦男 | 松田美佳 訳 / 春秋社
ちょうど1年前ぐらいに買っておいたのを
ようやく手をつけることができ、読了♪
買ったきっかけは
その頃、YouTubeにNHK公式(確か笑)が載せていて
見られるようになっていた動画
『こころの時代~宗教・人生~
ヴィクトール・フランクル それでも人生には意味がある』
というシリーズを見て興味が湧いたから
(たしか全5回のシリーズだったかな?)
ヴィクトール・フランクル(V・E・フランクル)さん
もの凄~くかいつまんで説明すると
ユダヤ人として、アウシュビッツを含むナチスの強制収容所に送られ
生きて還って来た、オーストリアの精神科医・心理学者
つまり、文字通り"真の地獄"を
その目で見て、くぐり抜けてきた奇跡の御方
そのフランクルさんが
収容所解放から1年ほど経って行われ講演を収めたのが本書
なので、基本的に、精神科医・心理学者として
(もちろん収容所体験を含め)様々な人間・患者との交流から生まれた
臨床的・実体験的な分析が語られている1冊
なので(笑)、
地獄の強制収容所体験の
ショッキングな部分を期待して読むと肩透かしをくらいます(笑)
そういう部分が読みたいなら
みすず書房から出ている、これまたベストセラーな代表作である
『夜と霧【新版】』と『夜と霧 ドイツ強制収容所の体験記録』
の2冊を読んだ方が良さそう
(いずれ読んでみるつもり)
~ ~ ~
ご興味湧かれた方は実際に読んでいただくとして、、(笑)
講演の内容は、平易な言葉ではあるけれども
なかなか1回読んだだけでは難しい箇所もあったね
2~3回読むともっと理解がグッと深まるかもしれない
訳者である山田邦男氏による
本編終わってからの結構長めの解説
これが本編を補強・理解するのに
なかなか役に立つパートで、、
「フロイト(本書中だとフロイド)の精神分析」と
「アドラーの心理学」
を高次元で融合できるようなものがフランクルさんの思想
と言うことができそうだ
「生きる意味とは?」だったり
「自殺がなぜいけないのか?」だったり
誰もが人生で一度は考えたことがあるであろうテーマが
興味深く丁寧に語られていて、
自分的にも、
けっこう大事な視点を得ることが出来た1冊だった
けっこう大事な視点を得ることが出来た1冊だった
それは、本書の中でも「人生のコペルニクス的転回」と
位置付けられている、重要な思考法・思想なのだけれど
「確かに、、なるほどな~、、!」と思わせてくれるものだった
(これまた語弊・誤解があるとアレなので、詳細は本書を読んで理解していただきたいけれども)
自分が理解したものを簡潔に書くと、
「自分がこの人生に対して何を期待しているか?」ではなく
「自分がこの人生によって何を問われているか?何を求められているか?」という視点
この視点こそが、人生を"意味あるもの"として生きるために必要だ
ということ
強制収容所は、まさに
「夢も希望もなく、あるのは"死"しかない、という真の極限の状況」
そんな地獄の強制収容所であっても
絶望に打ちひしがれて死んでしまう人もいれば
心をなくさずに生きて還って来れた人もいる
その違いは何だったのか?
それこそが、上述の視点だったようだ
地獄の強制収容所においては
「"自分が"何を期待しているか?」という自己中心的・主観的な視点に立ってしまっては
"死しか見えない"極限状態では、"生きる意味"を失って、もはや生きることは出来ない
今まさに「ここで」「この瞬間」に
「自分が何を求められているのか?」
「人生から何を問われているのか?」
(これは本書には直接書いてなかったけれど、強制収容所では、例えば
「収容所の外に自分を待っている人がいる」→だから生きて還らねばならない
「自分にとってやらなければならない使命・仕事がある」→だから生きて還らねばならない
なんてことが挙げられるのかな / だから人間は社会的生物ということにもなってくる)
それを自分に問い
1個1個ずつ対応していく
1個1個ずつ対応していく
その繰り返しこそが人生であり、
そうした"問われているものごと" "人生からの要求"は、
たとえ極限状態にあったとしても、決して無くなることはない
(また、その問いの、スケールの"大小"は問題ではない)
たとえ、それが何らかの病気で、死を前にした末期患者であっても
フランクルさんは、本書で人生を"チェス"にも喩えていて
チェスでは、その場面その場面で対処し手を打って
問われている要求に答えを出していく
人生はまさにそれと似たようなもので、
問われている要求が気に食わないと言って
チェスの盤をひっくり返す行動を決して取ってはいけない、と
それはチェスをプレイしたとは言えない
自殺は、チェスで言えば"盤をひっくり返す行為"だ
つまり人生から"問われている要求"に答えようとせず
拒絶し、無意味に帰す行為であって
何の解決にもなっていない
だから、自殺はいけない、と
だから、自殺はいけない、と
(しかしチェスには"負け"という終着点があるが
人生だと"負け"たらどうなんだろう、、?
チェスでいう"負け"た人が自殺するのか、、?って今書いてて思った 笑
まあでも、チェスはあくまで喩え話で、"負けた"(と思える)あとでも答えるべき要求は尽きないのだろう)
~ ~ ~
ついつい
「"人生"の意味とは?」
なんて、主語が大きくなりがちだけれど
そういうもじゃないんだ、ということ
一般論になり得るような"人生の意味"を考えてもナンセンスで
「その人その人それぞれにとって」
「ここで」
「この瞬間に」
自分が何をなすべきか?
一回性で、唯一無二の問いを
自分に問い続け
それに対処し続けること
それが人生だ
その時に自然と"意味"が湧いてくる(←私の理解です)
それは何も、強制収容所という極限状態に限った話ではなくて
日常における仕事においてもそうだ、という話にもつながってくる
("事"に"仕える"と書いて仕事だ / かと言って、"労働の奴隷になれ"という話じゃあない)
そうした"人生からの要求"には
さまざまなやり方で対処ができるのだけれど
フランクルさんが第一に挙げていたのが
「"活動"で答える」という答え方
つまり、
「何かをすることで応答する」
すなわち、
「なにか活動する」
「なにか作品を創造する」ことで
人生が出す具体的な問いに答えるやり方
フランクルさんが
「なにか作品を創造する」ことを"人生からの要求"対処法に挙げていたのが
自分としてはちょっと嬉しかったな(笑)
本能的に"ものづくり"的な道に進んだ自分としては(笑)
やっぱり俺は間違ってなかったんだ♪ と(笑)
~ ~ ~
「神が希薄になってしまった」近現代(特に西洋史では)においては
やはり、「生きる"意味"」の実感としての獲得が重要な問題となっているわけで
あらゆるもののオートメーション化・機械化が進み
(AIの台頭してきた昨今、今後さらにそれは加速していくだろう)
自分が何をしているんだか、何のために生きているんだか、分からない
必ず死ぬのに、生きている意味なんかあるのだろうか?
そうした虚無的気分・ニヒリズムに陥ることって
ますます増えてくると思うし、克服する必要も出てくる
ますます増えてくると思うし、克服する必要も出てくる
そんな時代を生きて行かなければならない我々にとって
かなり有効な思想、まさに「コペルニクス的転回」な思想かと思う
みなさんも取り入れてみてはいかがでしょか?
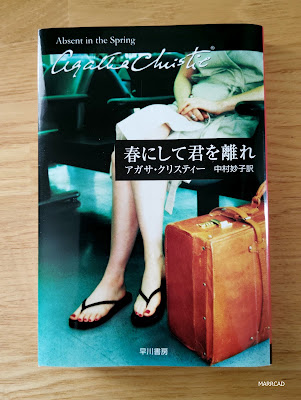_%E4%B8%AD%E6%9D%91%E5%A6%99%E5%AD%90(%E8%A8%B3)_IMG_20250606_155425c.jpg)








Comments